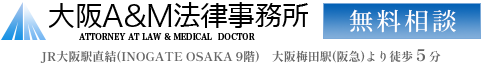交通事故による高次脳機能障害と損害賠償
交通事故で脳に損傷を受けたとして高次脳機能障害と思われる症状を呈する被害者の方の中には、画像検査所見などで器質的損傷が認められないということもあり、損害や、交通事故との間の因果関係が争われることもあります。
また、交通事故により高次脳機能障害を負ったという因果関係が認められたとしても、その後遺障害(後遺症)としての程度の評価も争いとなります。
交通事故により高次脳機能障害を負った場合、自賠責の後遺障害等級認定としては、「神経系統の機能又は精神に障害を残すもの」として、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号のいずれに当たるかが問題となります。
知能低下や、記憶障害などが著しく低下したような場合には、知能検査等で評価がしやすい面もありますが、行動障害や人格の変化を起因として、社会的行動障害があり就労が困難というような場合には、その評価が難しいこともあります。
また、高次脳機能障害を負った場合、脊髄損傷などで寝たきり状態ではなく、歩行機能などは維持されているがために、かえって、異常行動を監視する必要があり、付添や介護に手間がかかるということもあり、介護や付添の必要性や程度が、争いとなることもあります。
高次脳機能障害で見られる症状
高次脳機能障害で見られる症状には様々ありますが、主なものを挙げると以下の通りです。
①記憶障害
新しく起きた出来事や情報を覚えられないことも、事故前に遡って記憶がなくなってしまっていることもあります。
食べたものや買うべきものを忘れてしまったり、会話の中で話したことを忘れて、同じ内容を繰り返し質問してしまったりします。
②注意障害
外部からの刺激に対して注意を継続して持続させたり、同時にいくつもの刺激に対して注意を向けることが難しくなったりする障害があります。
例えば、周囲の状況に気が付かず適切なふるまいができなかったり、周囲に気を取られすぎて集中できなかったり落ち着かなかったりします。
また、同時並行で物事を進めることが難しくなったりします。
③遂行機能障害
遂行機能障害といって、一定の目的に向かって、段取りや手順を考えて効率よく実行をしていくことの障害があります。
遂行機能障害を患うと、自ら計画を立てて物事を実行することが難しくなったり、約束の時間を守るなどの段取りを踏むことが難しくなったりします。
④社会的行動障害
社会的行動障害は、感情や情緒のコントロールがうまくできなくなり社会生活に支障をきたしてしまう障害です。
かっとなって暴力を振るったり大声を出すなど怒りのコントロールが難しくなったり、自己中心的なふるまいが目立つようになったりします。
⑤言語障害
失語症など、言葉そのものの障害となることもあります。事故前と比べてなかなか言葉が出なくなったり言い間違えをしやすくなったりします。
また、相手の意図をくみ取ったり、相手に共感したりなどコミュニケーションに問題が生じることもあります。
高次脳機能障害の判断基準
以下の「主要症状等」「検査所見」が確認され、さらに「除外項目」に該当しない場合に、高次脳機能障害であると判断されます。
高次脳機能障害か否かの診断時期は、交通事故等脳の病変と考えられる外傷等の急性期症状を脱した後に行います。
「主要症状等」
- 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が、確認されている。
- 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
「検査所見」
MRI、CT、脳波などにより、認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。
「除外項目」
- 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状を欠く者は除外する。
- 診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
- 先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。
- 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる
高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害であると判断された場合に認定されうる後遺障害等級はどのようなものがあるでしょうか。症状や状態の程度により、重篤な順から、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号に認定される可能性があります。
まず、もっとも重篤な等級として、別表1に記載される1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」があります。1級1号は、生命維持に必要となる身の回りの処理について常に介護が必要と認められる場合に認められます。
次に2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」があります。一人での日常生活、食事、入浴、更衣などができないわけではものの、随時他人の手助けが必要な場合や、高次脳機能障害による認知症や幻覚、発作等のために他人の随時の監視が必要な場合に認められます。
3級3号として「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」があります。3級3号は、日常的な他人の監視や介護までは必要ないレベルだけれど、後遺障害のために円滑な意思疎通や作業に問題があって就労ができない場合に認定されます。
5級2号として「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」があります。5級2号は、神経の機能や精神的障害により、特に簡単な仕事以外には従事できない場合に認められます。
7級4号は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」となります。7級4号は、神経の機能や精神的障害により、簡単な仕事を除き就労できない場合です。5級2号よりは単独で遂行できる能力があり、時々他人から助言を受けられればある程度作業を進めることができるレベルです。
高次脳機能障害の後遺障害等級の中では最も軽度な等級が9級10号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」になります。9級10号は、神経の機能や精神的障害により就労できる仕事に制限が生じる場合に認定されます。
高次脳機能障害で後遺障害を認定してもらうための重要点
高次脳機能障害で後遺障害を認定してもらうための主な重要点は以下の通りです。
- 脳損傷を確認できる検査を受ける(証拠を残す)
- 事故後意識障害があったことを医師に記録してもらう
- 事故前と事故後で認知障害、行動障害、人格変化があることを記録する
脳損傷を確認できる検査を受ける(証拠を残す)
上述の高次脳機能障害の診断基準でも示しましたが、後遺障害等級認定を受けられる高次脳機能障害であると診断されるためには、検査によって脳の器質的病変があることについて検査所見があることが必要です。
中でも、頭部のCTやMRI等の画像検査は、客観的に病変部分を確認できるため重要な証拠になります。高次脳機能障害が疑われる場合は、早期にこれらの検査を受けておき証拠を残しておくことが重要です。
事故後意識障害があったことを医師に記録してもらう
交通事故直後に意識障害があった場合は、事故による高次機能障害の発生の可能性が高いことを裏付ける事情になりますので、後遺障害診断書などに主治医に記載してもらいましょう。特に意識障害が6時間以上継続していた場合には、後遺症として高次脳機能障害が残りやすいとされています。
事故前と事故後で認知障害、行動障害、人格変化があることを記録する
高次脳機能障害と認定されるためには、特色である認知障害、行動障害、言語障害、人格変化等の症状が現れていて、日常生活に制約が出ていると認定されることが重要になります。
こうした事情があることを主張するためには、医師の診断のほか、家族や周囲の人の報告も重要になります。主治医は事故前の被害者の様子は見ていないことも多いため、事故前事故後でどのくらい被害者の人格が変わってしまったのかを把握することが難しいからです。
高次脳機能障害が疑われる場合には、周囲の方は、交通事故後なるべく早期から、被害者の様子を注意深く観察し、何か異常や兆候がある場合には、日付とともに状況をメモしておきましょう。
高次脳機能障害で等級認定を狙う場合、専門知識がある弁護士に依頼する重要性
高次脳機能障害で後遺障害等級認定申請をする場合には、専門知識がある弁護士に相談することがおすすめです。
高次脳機能障害は見た目でわかりにくい脳の病変であり、もともとの性格や加齢・既往歴などと明確に峻別することが難しい場合もあります。
一方、認定される等級によって受け取ることができる金額が大きく異なるので、しっかりとした後遺障害等級認定申請書類を用意して適切な後遺障害等級認定を受ける必要があります。
専門知識がある弁護士にサポートすることにより、万全な後遺障害等級認定申請書類を用意することが期待できます。
例えば、高次脳機能障害の存在を主張するためには、適切な検査を受けることが重要です。外傷と違い目に見える証拠が残しづらいため、MRIやCT、脳波検査などで証拠を残す必要があるからです。サポートする弁護士にこうした知識があれば、どういった検査を受けるべきかアドバイスを受けることができます。
高次脳機能障害は重篤な障害であり、一言に交通事故といってもそれほど頻発する障害であるともいえません。
そのため、弁護士を選ぶ際には、高次機能障害の後遺障害等級認定申請を実際に経験している弁護士を選んだほうがよいでしょう。
ご自身やご家族が交通事故により高次脳機能障害を負った場合には、交通事故加害者との損害賠償問題については、早めに、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。